PEOPLE
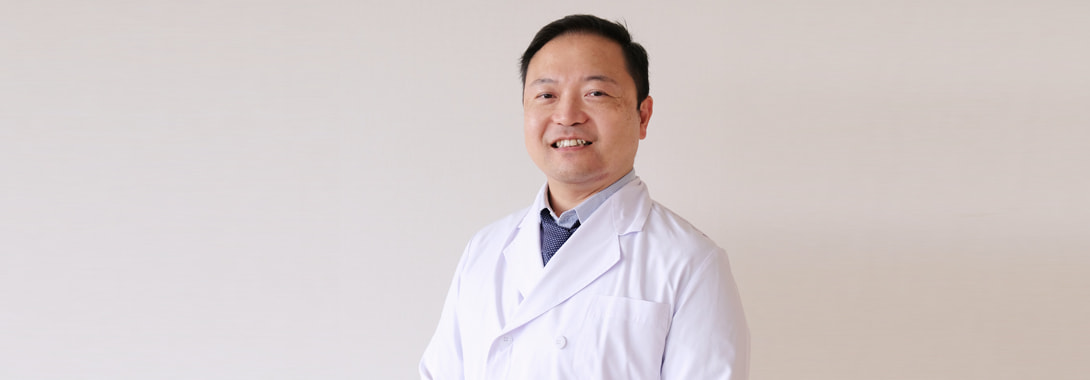
宮田 淳教授
経歴
資格・所属学会等
精神保健指定医 / 精神科専門医・指導医 / 日本統合失調症学会国際対応委員 / 日本生物学的精神医学会 評議員 / 日本精神神経学会 研究推進委員・国際委員・ICD-11委員 / Schizophrenia International Research Society(SIRS)Diversity Committee member / Psychopathology誌Editorial board member など
このたび、2023年10月1日付けで愛知医科大学精神科学講座の教授を拝命しました、宮田淳と申します。当講座は1972年の本学開校と同時に西丸四方教授が初代教授として就任されました。その後、大原貢教授、林拓二教授、兼本浩祐教授と引き継がれ、私で五代目となります。西丸先生はカール・ヤスパースの「精神病理学原論」などの翻訳で広く知られる、我が国の精神病理学を代表する方です。大原貢先生はてんかん・心理療法で知られます。林拓二先生は非定型精神病のCTを用いた脳画像研究という、先駆的な研究をされてきました。そして兼本先生はてんかん診療のバイブルである「てんかん学ハンドブック」を執筆された、てんかん診療・研究の第一人者です。このような愛知医科大学の幅広い伝統に、私の専門とする妄想・統合失調症の認知神経基盤研究および診療を加えることで、更に講座を発展させて行きたいと思います。
私は以下の基本方針のもとに教室を運営していきます。
なにより当講座の特色は、伝統的に自主性・多様性を尊重する自由な教室であることです。これまでに幅広い背景を持つ先生方が入局され、その多様性が当講座の強みになっています。また私自身は国際統合失調症学会(SIRS)のDiversity committeeでの活動を通じて、Evidence-based diversity & inclusionの推進に力を入れてきました。Diversity & inclusionを単なる掛け声に終わらせること無く、今後も医師として精神科医としての立場から貢献していきたいと思います。
最後に、臨床・教育・研究を通じて愛知医科大学医学部精神科学講座をより特色ある講座に育てていき、それにより患者さん・社会に貢献していきたいと思います。何卒よろしくお願い申し上げます。